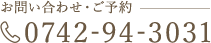- 感染性腸炎について医師が解説
- 感染性腸炎の原因
- 感染性腸炎の症状
- 感染性腸炎の一覧
- 症状が治まるまでの日数は?
- 感染性腸炎の検査
- 感染性腸炎の治療
- 回復を早めるための対処法と注意点
- 学校・仕事の復帰はいつからOK!?
感染性腸炎について医師が解説
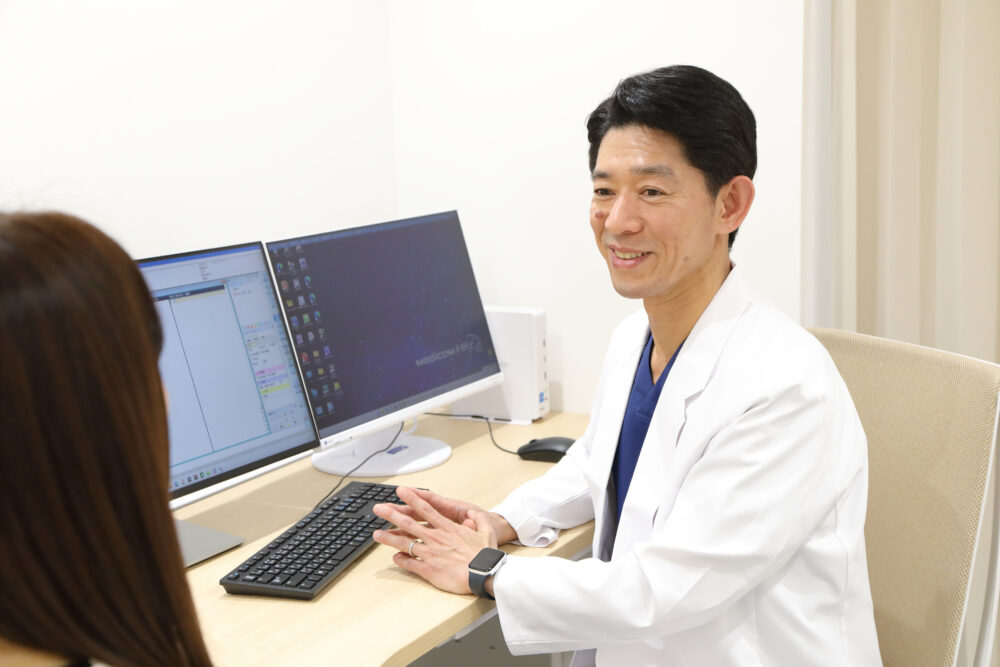 感染性腸炎は、ウイルス、細菌、寄生虫などの病原体による消化管(特に小腸や大腸)の感染症です。
感染性腸炎は、ウイルス、細菌、寄生虫などの病原体による消化管(特に小腸や大腸)の感染症です。
「食中毒」と呼ばれることもあり、主な感染経路は、感染者や動物との接触、不衛生な水や食品の摂取です。
下痢、腹痛、吐き気、発熱などの消化器症状が数日~1週間程度続き、自然治癒することが多いですが、脱水症状や電解質異常などの合併症を引き起こす場合もあります。
そのため、個人の衛生管理が予防に重要です。
感染性腸炎の原因
感染性胃腸炎は、主にウイルス性胃腸炎と細菌性胃腸炎に分けられます。
ウイルス性胃腸炎(嘔吐下痢症など)は冬場に多く、細菌性胃腸炎(食中毒など)は夏場に多い傾向があります。
ウイルス性腸炎
ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルス、サッポロウイルス、アストロウイルスといったウイルスが、口から入り小腸粘膜上皮に感染することで、ウイルス性胃腸炎を発症します。
感染した腸管はむくみ、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。
ウイルスの種類や個人差により、下痢ではなく、腹痛や膨満感のみの場合もあります。
感染経路は、感染者の吐物や便に含まれるウイルスへの接触です。
感染力の強いウイルスは、汚染された場所への接触でも感染する可能性があります。
普段から疲れを溜めないようにし、免疫力を高めておくことが重要です。
当院では、ウイルス性胃腸炎の治療も行っていますので、お気軽にご相談ください。
代表するウイルス
- ノロウイルス
- ロタウイルス
細菌性腸炎
細菌性腸炎(食中毒)は、原因となる食品を摂取後、5~72時間以内に発症します。
魚介類加工品、肉、卵、カキ氷、いずしなどを摂取した後に、下痢や腹痛が出た場合は、食中毒を疑う必要があります。
体力や免疫力によって、同じ食品を摂取しても発症に個人差が出ます。
特に、いずし摂取によるボツリヌス菌食中毒では、眼瞼下垂、複視、発語障害などの神経症状が現れ、重症の場合は死に至ることもあります。
速やかに当院にご相談ください。
代表する細菌
- サルモネラ菌
- カンピロバクター
- 黄色ブドウ球菌
- 病原性大腸菌
感染性腸炎の症状
- 発熱
- 腹痛
- 下痢
- 嘔吐
- 血便
| ウイルス性腸炎 | 細菌性腸炎 | |
| なし、または微熱程度のことが多い | 発熱 | 高熱になることがある |
|---|---|---|
| なし、または軽いことが多い | 腹痛 | 比較的強い |
| 嘔吐を伴うことも多い | 嘔吐 | 嘔吐は多くはない |
| 頻回の水様便、細菌性より重い傾向 | 下痢 | 軟便から水様便 |
| 無いことが多い | 血便 | 血便を認めることがある |
感染性腸炎の一覧
ウイルス性腸炎
ウイルス性腸炎は、ウイルスによる腸の炎症で、嘔吐や下痢、発熱などの胃腸症状を引き起こします。
主な感染経路は、汚染された食べ物や水の摂取、または感染者との接触です。
ノロウイルス
ノロウイルスは、ウイルス性腸炎の最も一般的な原因のひとつです。感染者の嘔吐物や便からウイルスが排出され、これを口に入れることで感染します。主な症状には、激しい嘔吐、下痢、腹痛、発熱などがあり、特に高齢者や免疫力が低下している人に重症化しやすいことがあります。感染後1~2日で症状が現れ、通常は1~3日以内に回復します。
ロタウイルス
ロタウイルスは特に乳幼児や小児に多く見られるウイルス性腸炎の原因です。感染すると、急性の下痢、嘔吐、発熱が見られ、脱水症状を引き起こすことがあるため、早期の水分補給が重要です。ロタウイルスは、便から直接または汚染された物品を通じて感染します。予防にはワクチン接種が有効とされています。
細菌性腸炎
細菌性腸炎は、細菌の感染によって引き起こされる腸の炎症で、食中毒の一種としても知られます。主な原因は、不衛生な食べ物や水の摂取です。症状には、下痢(血便を伴うこともある)、発熱、腹痛、吐き気などが含まれます。治療は抗生物質や水分補給が中心ですが、重症化を防ぐためにも早めの受診が重要です。
サルモネラ菌
サルモネラ菌は、細菌性腸炎の原因としてよく知られており、生肉や卵、汚染された食品を食べることで感染することがあります。症状としては、腹痛、下痢、発熱、吐き気があり、重症の場合には血便を伴うことがあります。感染後6~72時間以内に症状が現れ、通常は1週間以内に回復しますが、高齢者や免疫力が低い人では注意が必要です。
カンピロバクター
カンピロバクターは、細菌性腸炎を引き起こす最も一般的な細菌の一つで、特に未調理または不十分に調理された鶏肉が感染源となります。主な症状には、下痢、発熱、腹痛があり、しばしば下痢には血が混じることがあります。治療には、抗生物質が使われることもありますが、軽症の場合は水分補給と休養で回復します。
黄色ブドウ球菌
黄色ブドウ球菌は、細菌性腸炎の原因となる病原菌の一つで、食物中の菌が原因で感染します。症状には、激しい嘔吐、下痢、腹痛、発熱があり、急性の発症が特徴です。黄色ブドウ球菌による食中毒は、特に加熱しない食品や不衛生な環境で発生しやすいです。症状は通常、数時間以内に現れ、軽症の場合は特別な治療を必要としないことがあります。
病原性大腸菌
病原性大腸菌は、腸内に存在する細菌の一種で、特に食肉や生野菜などから感染します。病原性大腸菌による感染は、腹痛、下痢、時には血便を伴い、重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こすことがあります。感染後数日以内に症状が現れ、適切な治療を受けることが必要です。感染拡大を防ぐためには、食品の適切な取り扱いや衛生管理が重要です。
症状が治まるまでの日数は?
回復期間は、病原体や患者様の状態、治療への反応によって異なります。
ウイルス性腸炎(ノロウイルス、ロタウイルスなど)の場合、症状は通常2~3日で軽減しますが、完全回復には1週間程度かかります。
高齢者や免疫力の低い方は、さらに時間を要する場合があります。
また、症状回復後も1ヶ月ほど便にウイルスが排出されるため、衛生管理に注意が必要です。
細菌性腸炎(サルモネラ、カンピロバクター、特定の大腸菌など)の場合、適切な抗生物質治療により5~7日で改善しますが、潜伏期間や症状の重さにより長引くこともあります。
寄生虫が原因の場合、適切な薬剤投与により1~2週間で症状は軽減しますが、完全に排除されるまでは数週間かかる場合があります。
いずれの場合も、十分な水分・栄養摂取と休息が重要です。
症状が改善しても感染力が残存する可能性があるため、個人衛生に引き続き注意してください。
感染性腸炎の検査
 感染性胃腸炎の原因特定には便検査が必要です。
感染性胃腸炎の原因特定には便検査が必要です。
便中の抗原を調べる検査や、便を培養して病原菌を特定する検査があり、ノロウイルス・ロタウイルスは迅速抗原検査(便中抗原検査)は、15~30分で診断可能です。
また、血液検査で病原菌の毒素や抗体を測定できる場合もあります。
感染性腸炎の治療
感染性腸炎の時は以下のような治療を行います。
- 食事は症状に応じて制限し、水分摂取はOS-1やポカリスエットなどの経口補水液を推奨しますが、重度の脱水症状の場合は点滴による入院管理を検討します。
- 整腸剤、乳酸菌製剤、制吐剤などを用います。
- 下痢止めは原則として使用しません。
- 細菌性食中毒は多くの場合、対症療法で自然軽快するため、抗菌薬は高齢者や免疫不全などの場合に限定的に使用します。症状が重い場合、抗菌薬投与で罹病期間を1~2日短縮できる可能性があるため、コレラ、細菌性赤痢、サルモネラ腸炎、早期のカンピロバクター腸炎、チフス、パラチフス、渡航者下痢症などで使用されます。
- 原因菌が不明の場合は、ホスホマイシンやマクロライド系やニューキノロン系抗菌薬を選択します。
回復を早めるための
対処法と注意点
日常生活の改善として、消化の良い食事、暴飲暴食の回避、十分な咀嚼、こまめな水分補給を心がけましょう。
下痢が続くと脱水症状になる恐れがありますので、特に水分補給は意識的に行ってください。
食事について
感染性胃腸炎の際には、消化しにくい食べ物は避け、消化しやすい食べ物を摂取するようにしましょう。
消化しやすい食べ物
- ご飯
- おかゆ
- 素うどん
- 食パン
- スープ
- 乳酸菌飲料
- ヨーグルト
- 乳製品(牛乳、豆腐、チーズ)
- 加熱した卵
- 火の通った野菜
- 脂身の少ない肉類
- 加熱した白身魚、はんぺん
- 煮た大根やニンジン
- りんご、バナナ
- ヨーグルト
- プリン、ゼリー など
消化しにくい食べ物
- 脂肪の多い食事
- 海藻
- リンゴ、桃、梨(なし)、プルーン など
- たこ、イカ
- 貝類
- ごぼう、たけのこ、れんこん、山菜
- きのこ類、こんにゃく類など
下痢止めの使用は控える
感染性胃腸炎の際、市販の下痢止めを使用する方もいるかもしれませんが、下痢止めは一時的な効果しかなく、根本的な治療にはなりません。
下痢はウイルスや細菌を体外へ排出する役割があるため、炎症が治まるまでは下痢止めを使用せず、自然経過に任せることをお勧めします。
お腹を温めるようにする
感染性胃腸炎の際は、お腹を温めるようにしましょう。
冷えると血流が悪化し、交感神経が優位になることで消化不良を起こし、下痢が悪化することがあります。
学校・仕事の復帰は
いつからOK!?

感染性胃腸炎は、症状が治まった後も数週間は便から菌が排出され、他人に感染する可能性があります。
排便後の手洗いや手指消毒を徹底することが重要です。
学校や職場を休む期間は明確な規定がなく、「解熱し、腹痛や下痢などの症状が落ち着くまで」が目安となります。
病原菌によっては、症状が改善した後も数日間~2週間程度排菌が続くため、必要に応じて迅速検査や培養検査で病原菌を特定します。
職場復帰については勤務先に確認し、接客業や調理などでは各社の基準に従ってください。
欠勤に関することや診断書の発行については、当院にご相談ください。