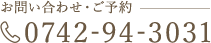過敏性腸症候群(IBS)
について医師が解説
 過敏性腸症候群は、大腸に炎症やポリープなどの異常がないにもかかわらず、腹痛、便通異常、膨満感などの症状が長期的に続く疾患です。下痢型、便秘型、混合型などに分類され、原因は明確ではありませんが、腸の機能異常や知覚過敏、ストレスなどが関係していると考えられています。
過敏性腸症候群は、大腸に炎症やポリープなどの異常がないにもかかわらず、腹痛、便通異常、膨満感などの症状が長期的に続く疾患です。下痢型、便秘型、混合型などに分類され、原因は明確ではありませんが、腸の機能異常や知覚過敏、ストレスなどが関係していると考えられています。
器質的異常がないため、心理的な問題や体質と考えられがちですが、専門医による治療で改善が期待できます。
長引く症状でお困りの際は、当院へご相談ください。
過敏性腸症候群の種類
過敏性腸症候群は、便秘型、下痢型、混合型に大きく分けられます。
下痢型
下痢型の過敏性腸症候群では、強い腹痛を伴う水様便が1日に数回みられ、外出をためらうほど生活に支障が出る場合もあります。
便秘型
便秘型の過敏性腸症候群では、腹痛を伴い、少量の硬い便しか出ず、強くいきんでも残便感があるなど、排便困難な状態になります。
混合型
混合型の過敏性腸症候群は、強い腹痛とともに、便秘と下痢を繰り返します。
過敏性腸症候群の症状チェック
下記の症状が続く場合は、過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。
他の重篤な疾患の可能性もあるため、ご相談ください。

- 体重が減少する
- 就寝中に腹痛で目が覚める
- 残便感がある
- 1日の排便回数が不規則
- 便秘が続く、またはコロコロとした便が出る
- お腹の調子が長期間にわたり悪い
- 下痢や便秘などの便通異常が続いている
- 便の形が悪いのが続いている
- 腹痛があるが、排便をすると一時的に痛くなくなる
過敏性腸症候群の原因は
ストレス?!
過敏性腸症候群は、腸神経系の調節不全により腸が過敏になり、下痢や便秘などの症状が現れます。
日本では10人に1人が罹患し、特にストレスを受けやすい10~30代の若い世代に多くみられます。
ストレス
過敏性腸症候群の原因は、精神的・身体的ストレスと考えられています。
ストレスは自律神経の内分泌を過剰に促進し、腸の蠕動運動異常を引き起こし、下痢や便秘につながります。
急性の感染性腸炎
細菌やウイルス感染による急性腸炎がきっかけで、腸が過敏になる場合があります。
過敏になった腸に、ストレスやPM2.5などの環境汚染物質が加わると、腸炎が慢性化し、過敏性腸症候群の症状が現れることがあります。
腸内環境の悪化
腸内細菌は、善玉菌が優位な状態が理想的です。
抗生物質の服用や体調変化などで悪玉菌が増殖し、腸内細菌のバランスが崩れると腸に炎症が起こり、過敏性腸症候群を発症するきっかけとなることがあります。
過敏性腸症候群の検査
過敏性腸症候群が疑われる際は、以下のような検査を行います。
- 問診
- 血液検査
- 便潜血検査
- 大腸内視鏡検査
 大腸カメラ検査は当院で実施しており、日本消化器内視鏡学会専門医が精度の高い検査と診断を行います。
大腸カメラ検査は当院で実施しており、日本消化器内視鏡学会専門医が精度の高い検査と診断を行います。
腸に異常がないことを確認した上で、過敏性腸症候群と診断します。
過敏性腸症候群の治療
患者様お一人おひとりの症状やタイプ、お悩みに寄り添い、当院では最適な治療を提供いたします。
些細なお困りごとでもお気軽にご相談ください。
生活習慣の見直しに関しても、分かりやすくご説明し、無理なく続けられる改善をサポートいたします。
当院では、患者様の症状改善を最優先に考え、診療を進めてまいります。
生活習慣の見直し
食習慣
 規則正しい時間に1日3食の食事を摂り、暴飲暴食は控えましょう。
規則正しい時間に1日3食の食事を摂り、暴飲暴食は控えましょう。
水分も適度に補給してください。
食物繊維を豊富に含み、栄養バランスの良い食事を心がけ、アルコールやカフェイン、唐辛子などの刺激物はなるべく避けましょう。
運動
階段を使う、少し速めに歩くなど、日常生活の中で軽い運動を習慣化しましょう。
休息・睡眠
趣味やスポーツでストレスを発散し、十分な睡眠と休息を確保しましょう。
夏場でも湯船に浸かり、体を温めることをお勧めします。
薬物療法
 当院では、患者様の症状、体質、生活習慣、既往歴などを考慮し、最適な薬を処方いたします。
当院では、患者様の症状、体質、生活習慣、既往歴などを考慮し、最適な薬を処方いたします。
腸の症状を改善する薬は種類が多く、効果や作用機序も様々です。
新しい薬も次々と開発されています。
症状の変化に合わせて処方内容も見直しますので、再診時には現在の状況を詳しくお伝えください。
薬の効果や服用タイミングなど、ご不明な点はいつでもご相談ください。
過敏性腸症候群を予防・対策
胃腸を強化するための
規則正しい生活習慣
 過敏性腸症候群の予防・改善の基本は、規則正しい生活です。
過敏性腸症候群の予防・改善の基本は、規則正しい生活です。
毎日の起床・就寝時間や、3食の食事時間を一定にすることで、自律神経と腸内環境を整えましょう。
ウォーキングなどの運動習慣や、こまめなストレス解消も、自律神経のバランスを保つために重要です。
起床
体内時計を整え、睡眠ホルモンであるメラトニンの生成・分泌を促すためにも、日光を浴びましょう。
また、夕食は軽めに摂ることをお勧めします。
朝食
胃腸の目覚めを促し、その運動機能を高めるため、朝食は必ず摂りましょう。
昼食
唾液による消化を促し、胃の負担を軽減するために、食事はよく噛んで食べましょう。
間食
胃腸を休ませるために、間食は避け、4時間何も食べない時間を作るようにしましょう。
運動
ウォーキングなどの有酸素運動に加え、筋トレやストレッチを組み合わせた軽い運動を習慣にしましょう。
夕食
消化の良いものを中心に、脂っこいものは控えめにしましょう。
特に中高年の方は、腹七分目を目安に、夕食は軽めに摂りましょう。
就寝
リラックスして就寝前に過ごし、7時間程度の睡眠時間を確保し、毎日決まった時間に寝ましょう。