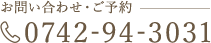大腸憩室炎について医師が解説
 加齢に伴い増加する大腸壁の外側への突出を、大腸憩室といいます。
加齢に伴い増加する大腸壁の外側への突出を、大腸憩室といいます。
腸管内圧の上昇は、便秘や食物繊維摂取不足が原因と考えられています。
大腸憩室の発生部位は、右側型(盲腸~上行結腸)と左側型(S状結腸)に分類されます。
大腸憩室の大半は無症状ですが、憩室の炎症による腹痛を伴う憩室炎や、憩室出血が起こる場合もあります。
高齢化と食生活の欧米化に伴い、憩室出血や憩室炎といった大腸憩室疾患の患者様が増加しています。
おならが溜まると
憩室炎になる!?
 腸管内の圧力上昇が憩室形成の一因です。
腸管内の圧力上昇が憩室形成の一因です。
便秘やいきみによる圧力上昇だけでなく、おならが溜まることでも腸壁が外側に膨らみ、憩室が形成されます。
当院では、患者様におならや便を我慢しないこと、適度な運動(散歩やストレッチなど)、腸内環境を整えるためのビフィズス菌入りヨーグルトの摂取をお勧めしています。
大腸憩室症の原因
大腸の腸管壁の一部が袋状に外へ突出している状態が憩室です。
加齢と共に増加し、一度できると元には戻りません。
腸管内圧の上昇(慢性的な便秘など)により、腸壁の弱い部分が外側に膨らむことが原因です。
喫煙、肥満、運動不足、赤身肉の多い食事や食物繊維の少ない食事なども関連しています。
当院では、患者様の状態に合わせた適切な指導を行っています。
大腸憩室症の症状は無症状
憩室自体は、合併症がなければ治療の必要はありません。
多くの場合無症状で、大腸カメラ検査やCT検査などで偶然発見されます。
S状結腸に多数の憩室ができると腸管が狭窄し、腹部の張り、便通異常、腹痛などの症状が現れることがあります。
注意すべき合併症として、憩室出血と憩室炎の2つが挙げられます。
憩室炎になると
腹痛や発熱などの症状が
出ることもある
 憩室炎は、憩室に溜まった糞便により細菌が繁殖し炎症を起こす状態で、発熱、腹痛、下痢などの症状が現れます。
憩室炎は、憩室に溜まった糞便により細菌が繁殖し炎症を起こす状態で、発熱、腹痛、下痢などの症状が現れます。
重症化すると腸管穿孔や膿瘍形成の危険性もあるため、疑わしい場合は血液検査や腹部CT検査で炎症の程度を評価します。
※CT検査が必要な場合は、高度医療機関へのご紹介をいたします。
憩室出血になると
血便が出ることもある
憩室出血は、憩室内の血管が破綻し出血する状態で、肥満やNSAIDs・抗血栓薬の服用がリスクとなります。
腹痛や発熱は伴いませんが、多くは突然の血便で気付かれます。
大量出血の場合は、大腸カメラ検査で出血部位を特定し止血処置を行ったり、輸血が必要になることもあります。
大腸憩室症の検査
当院では、大腸憩室の診断に大腸カメラと血液検査を用います。
CT検査が必要な場合は、高度医療機関へのご紹介をいたします。
憩室炎
 血液検査では、憩室炎で炎症反応の数値上昇がみられます。
血液検査では、憩室炎で炎症反応の数値上昇がみられます。
腹部CTでは、憩室周囲の大腸壁の肥厚や脂肪組織の炎症所見が確認できます。
炎症が強く穿孔が生じている場合は、これらの所見に加え、通常は見られない空気の存在が認められることがあります。また、球状の膿の塊が確認されれば、膿瘍形成の可能性があります。
※CT検査が必要な場合は、高度医療機関へのご紹介をいたします。
憩室出血
 検査には、血液検査と大腸カメラを用います。
検査には、血液検査と大腸カメラを用います。
血液検査で貧血の程度を確認し、大腸カメラで出血箇所を特定し内視鏡的止血術を施行します。
つまり検査と治療を同時に行います。
憩室が多発している場合は出血部位の特定が難しく、血便後24時間以内では正確な診断率は22~40%です。
大腸カメラで憩室が確認できない場合は、血管造影検査や造影CTを行うこともあります。
※CT検査が必要な場合は、高度医療機関へのご紹介をいたします。
大腸憩室症の治療
憩室炎と憩室出血の治療では、腸管安静のため数日間の絶食が必要です。
水分・栄養不足を防ぐため、提携先の高度医療機関にご入院いただき点滴治療を行うことがあります。
憩室炎
腸管安静と並行し、抗菌薬を投与して細菌の増殖を抑制します。
多くの場合、抗菌薬で改善しますが、穿孔や膿瘍形成には、膿瘍ドレナージや手術などの追加治療が必要になります。
憩室出血
 大腸カメラで憩室の出血箇所を確認後、医療用クリップやスネアで止血します。
大腸カメラで憩室の出血箇所を確認後、医療用クリップやスネアで止血します。
憩室炎と憩室出血は適切な治療で改善しても再発しやすい疾患です。
無症状で進行することが多いため過度な心配は不要ですが、治療歴があり腹痛や血便などの症状が出た場合は、速やかに当院を受診ください。
大腸憩室症の方に
おすすめの食事法
 急性期の食事は、消化の良い食品(白米、うどん、白パン、麺類、ヨーグルト、チーズ、豆腐、白身魚、牛乳など。「白い食べ物」と覚えておくと便利です)を中心に、腸への負担を軽減しましょう。
急性期の食事は、消化の良い食品(白米、うどん、白パン、麺類、ヨーグルト、チーズ、豆腐、白身魚、牛乳など。「白い食べ物」と覚えておくと便利です)を中心に、腸への負担を軽減しましょう。
コーヒーやチョコレートなどは腸を刺激するため避けましょう。
腹痛が治まり炎症が落ち着いたら、食物繊維を多く含む食品(大根、ゴボウなどの根菜類、エノキ、マイタケ、シイタケなどのキノコ類、ワカメ、ヒジキなどの海藻類、大豆製品など)を積極的に摂りましょう。
食物繊維は便のかさを増し、大腸の蠕動運動を活発にして便通を促し、腸内圧を下げ、憩室炎の予防に繋がります。
当院では、患者様の状態に合わせた食事指導も行っています。