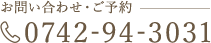血便に気づいたら
お早めにご相談を
 血便や下血は様々な疾患で起こり、「痔」と自己判断するのは危険です。
血便や下血は様々な疾患で起こり、「痔」と自己判断するのは危険です。
お早めに当院で検査を受けることをお勧めします。
血便や下血の原因となる疾患、対処法、検査方法などをご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
血便について
赤い血が混じる便を血便といい、肛門や大腸などの下部消化管の出血で起こります。
出血部位が肛門だと鮮やかな赤色、大腸だと暗赤色になります。
血便以外にも、下痢、便秘、残便感、発熱、痛み、倦怠感、嘔吐など様々な症状を伴う場合があり、重大な疾患が隠れていることもあります。
黒色便・タール便との違い
血便は下部消化管(肛門や大腸など)の出血ですが、下血は上部消化管(胃や十二指腸など)の出血です。
上部消化管の出血は、消化酵素や胃酸の影響で黒色(コールタール状)の便となりますが、大量出血では暗赤色の便になることもあります。
便潜血との違い
肉眼で確認できる血液が混ざった状態が血便ですが、肉眼で確認できない少量の血液混入を見つけるために便潜血検査を行い、陽性の場合には血液が混ざっていると判定されます。
血便とストレスとの関係
現代社会でストレスを完全に避けることは困難です。
仕事、勉強、家事、育児などでストレスを感じている時に血便が出ると不安になります。
ストレスが直接血便の原因となることはありませんが、強いストレスや不摂生から胃潰瘍や過敏性腸症候群などを発症し、結果として出血を伴うことがあります。
血便の色から考えられる疾患
鮮血便
見た目
鮮やかな赤い血液が混入している、あるいは付着している
出血が予測される部位
直腸、肛門
疑われる疾患
- 切れ痔
- いぼ痔(内痔核)
- 直腸潰瘍
- 直腸ポリープ
- 直腸がん
- 潰瘍性大腸炎
- 毛細血管拡張症
- S状結腸憩室出血
暗赤色便
見た目
レンガ色や暗い赤色の便
出血が予測される部位
小腸、大腸の奥
疑われる疾患
- 虚血性腸炎
- 感染性腸炎
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
- 上行結腸憩室出血
- メッケル憩室出血
- 大腸ポリープ
- 大腸がん
- 小腸潰瘍
黒色便
見た目
粘り気があって全体的に真っ黒なタールの見た目をした便
出血が予測される部位
食道、胃、十二指腸
疑われる疾患
- 逆流性食道炎
- 食道がん
- 食道・胃静脈瘤破裂
- 胃潰瘍
- 胃ポリープ
- 胃がん
- 十二指腸潰瘍
- 毛細血管拡張症
血便をともなう病気
血便は痔以外にも様々な疾患で起こります。
症状や出血の状態は疾患によって異なり、似た症状の疾患もあるため、自己判断せず、当院にご相談ください。
痔
痔による血便は、痔核(いぼ痔)と裂肛(切れ痔)が原因として考えられます。
いぼ痔は、慢性的な便秘や下痢による肛門への負担増加でうっ血し、こぶ状の痔核ができる状態です。
切れ痔は、硬い便により肛門が裂ける状態です。
痔による血便は、鮮やかな赤い血液が、排便時に垂れたり、便の表面に付着したり、トイレットペーパーに付いたりします。
出血量は様々ですが、ほとんどの場合肛門痛を伴います。
大腸がん
大腸がんと痔の症状は類似しており、大腸がんにもかかわらず痔の治療を希望される患者様もいらっしゃいます。
初期の大腸がんは自覚症状が少ないのですが、進行すると、下痢や便秘の頻発、粘液便、細便、暗赤色の血便、腹部膨満感、腹痛、残便感、体重減少、貧血、全身倦怠感などが現れます。
早期発見のためにも、気になる症状があれば当院にご相談ください。
大腸ポリープ
大腸ポリープは、大腸粘膜にできる良性病変で、腫瘍性と非腫瘍性があります。
腫瘍性のポリープはがん化のリスクがあるため切除が必要です。
初期は自覚症状が少ないのですが、大きくなると下痢、腹痛、腹部膨満感、粘液便、排便困難、排便時出血などの症状が現れ、大腸がんと似た症状が出るため注意が必要です。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は厚生労働省指定の難病で、原因は不明ですが免疫異常の関与が示唆されています。
どの年代でも発症する可能性がありますが、男性は20~24歳、女性は25~29歳がピークで、発症割合は男女ほぼ同等です。
主な症状は、血と粘液が混じる赤黒い下痢便で、激しい腹痛、発熱、全身倦怠感、体重減少、食欲低下などを伴うこともあります。
虚血性大腸炎
虚血性大腸炎は、大腸への血流障害により大腸粘膜に潰瘍ができる疾患で、60歳以上に多く発症します。
特徴としては、突然の腹痛(主に左下腹部)が出現し、次第に下痢、そして血便へと変化します。
鮮血のみの場合もあります。
細菌性腸炎
感染性腸炎は、腸炎ビブリオ(魚介類)、病原性大腸菌(牛肉)、サルモネラ(卵)、カンピロバクター(鶏肉)などの細菌感染で起こります。
嘔吐、血便、下痢、腹痛、発熱が主な症状です。ウイルス性腸炎もありますが、血便を伴うのは主に細菌性腸炎です。
大腸憩室出血
大腸憩室は、腸管内圧の上昇により腸壁がポケット状に飛び出したもので、加齢とともに腸壁が薄くなる60歳以上に多くみられます。
憩室ができると、10~20%の確率で憩室出血や憩室炎などの合併症を引き起こす可能性があり、憩室出血では急激な大量出血を伴う血便が起こることもあります。
クローン病
クローン病は、消化管全体に炎症や潰瘍ができる原因不明の炎症性疾患で、10~20代に好発します。
主な症状は下痢と腹痛で、粘血便が見られることもあります。
痔ろうによる肛門痛、栄養障害による体重減少、炎症による発熱なども起こり、寛解と再燃を繰り返します。
黒色便・タール便を伴う病気
血便の検査
 痔が疑われる場合は、触診と肛門鏡を用いた診察を行います。
痔が疑われる場合は、触診と肛門鏡を用いた診察を行います。
患者様には横向きに寝ていただき、医師が麻酔入りのゼリーとゴム手袋を使用し、痛みを最小限に抑えながら触診と肛門鏡検査を行います。
胃や十二指腸疾患が疑われる場合は、胃カメラ検査を実施します。
当院では鼻からの挿入で負担を軽減していますが、ご希望であれば鎮静剤を用いた経口挿入も可能です。
大腸疾患が疑われる場合は、大腸カメラ検査を行います。
鎮静剤を用いてウトウトした状態で、肛門からスコープを挿入し大腸の状態を観察します。初期のがんの発見や、ポリープの切除も可能です。
血便の治療
 血便の原因疾患が特定できれば、適切な治療を行います。
血便の原因疾患が特定できれば、適切な治療を行います。
当院は消化器内科と肛門内科の専門診療に対応しており、幅広い疾患の治療が可能です。
高度な検査や治療、入院が必要な場合は、連携先の高度医療機関をご紹介します。